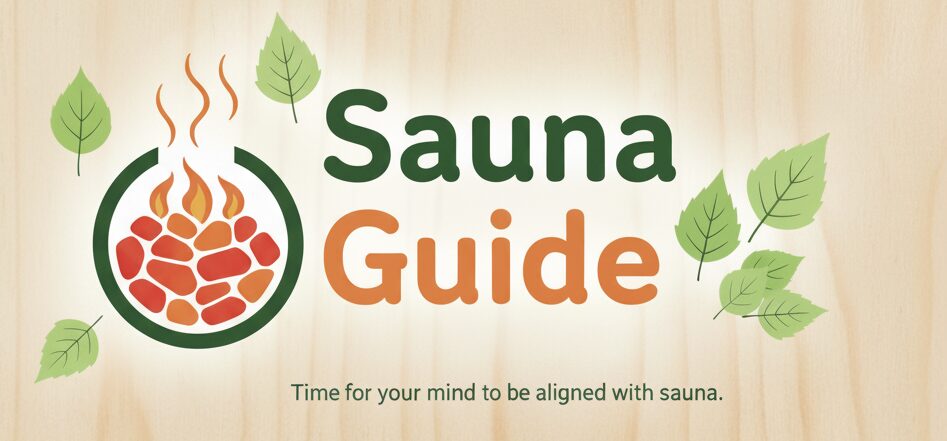「今日のサウナ、温度計は90℃なのに、なんだかすごく熱いな…」 「この前は同じ90℃でも、もっと長く入っていられたのに…」
そんな風に感じたことはありませんか?
かつての僕もそうでしたが、多くのサウナーは、単に温度計の数字や座席の上段・下段といった情報だけで判断しがちです。
僕が初めてオートロウリュを体験した時、室温は90℃。
最上段に座り「ちょうどいいな」と思ったのも束の間、オートロウリュが始まり蒸気が降り注ぎ、送風が始まった瞬間…
指先まで痺れるような刺激的な熱さを感じ、普段は10分程度入っていられるのに、たった5分で限界に達し、退室してしまいました。
あの時感じたのは、単なる「温度」ではなく、「湿度と風が作り出す、鋭い熱」でした。
サウナの本当の気持ちよさを決めるのは、温度計の数字だけではありません。
上級者(ガチ勢)ほど、「温度」「湿度」「風」という3つの要素と、「サウナ室の構造」を重視しています。
この記事では、サウナの基本的な種類から、上級者が実践する「最高のサウナ室の見つけ方」までを徹底解説します。
この記事を読めば、もう温度計の数字だけで施設を選ぶことはなくなるはずです。
「サウナ室の違い」を深く理解し、あなたにとっての「最高のサウナ」を見つけるお手伝いをさせてください。
1. 【基本】サウナの2大分類
サウナ室の違いを理解する第一歩として、まずはサウナの「2つの大きな分類」を知りましょう。

世の中のサウナは、基本的にこのどちらか(またはその中間)に分類されます。
| 項目 | 乾式サウナ (ドライサウナ) | 湿式サウナ (ウェットサウナ) |
|---|---|---|
| 特徴 | 高温・低湿 | 低温・高湿 |
| 温度 | 80℃~100℃ | 40℃~60℃ |
| 湿度 | 10%~20%前後 | 40%~100% |
| 通称 | カラカラ系、昭和ストロング系 | しっとり系、ミスト/スチーム |
| 体感 | ピリピリとした刺激、息苦しさ | じわじわ温まる、肌や髪に優しい |
| 楽しみ方 | 短時間集中、強烈な温冷交代浴 | 長時間リラックス、美肌効果 |
① 乾式サウナ(ドライサウナ)
日本のサウナ施設で最も一般的なタイプ。湿度が低く空気が乾燥しているため、温度計の数字以上にピリピリとした肌の刺激を感じることも。
テレビや12分計が設置されていることが多いのも特徴です。
② 湿式サウナ(ウェットサウナ/スチーム)
乾式とは対照的に、温度は低いものの湿度が非常に高いタイプ。
ボイラーで蒸気を発生させる「スチームサウナ」や、霧状の水を噴射する「ミストサウナ」が代表的。
息苦しさがなく、リラックスや美肌効果を求める人に向いています。
2. 熱源とロウリュで変わる!サウナの主な種類
サウナの基本分類(乾式・湿式)を理解したところで、次は私たちが実際に施設で出会う、より具体的なサウナの種類を見ていきましょう。
熱の発生源や「ロウリュ」の有無によって、体感は全く異なります。

① フィンランド式サウナ(ロウリュ)
- 特徴: 中温・多湿(70℃~90℃)。ロウリュによる湿度コントロールが前提。
- 楽しみ方: 瞑想、深いリラックス、熱の「質」を味わう
乾式サウナをベースに、熱したサウナストーンに水をかけて蒸気(=ロウリュ)を発生させ、意図的に湿度を高めるのが「フィンランド式」です。
日本のカラカラなドライサウナとは違い、湿度があるため呼吸がしやすく、熱が体の奥までじっくりと浸透してくるのが特徴です。
僕がサウナの種類に、興味を持つきっかけとなったのは、初めての「セルフロウリュ」体験でした。
そっと柄杓(ひしゃく)でストーンに水をかけると、「ジュワ〜ッ!」という心地よい音と共に、熱い蒸気が天井を伝ってふわりと降りてきたのです。
一瞬で室内の湿度が上がり、熱が蒸気と共に降り注ぎ肌を包み込む感覚…。
自分の手でサウナ室の環境に変化を与えた、あの瞬間の感動は忘れられません。
この「熱の質」を自分でコントロールできるのが、フィンランド式の最大の魅力です。呼吸が楽な環境は、瞑想にも最適で、より深い「ととのい」を目指す人には最高のサウナと言えるでしょう。
② ドライサウナ(高温・低湿)
- 特徴: 高温・低湿(90℃~100℃以上)。輻射熱(※)が主体。
- 楽しみ方: 短時間集中、水風呂との強烈な温冷交代浴
(※輻射熱:ストーブから発せられる赤外線などが、空気を介ず直接体を温める熱のこと)
日本の多くの施設で採用されている、いわゆる「昭和ストロング」とも呼ばれるスタイルです。
湿度が極めて低いため、肌がピリピリと焼けるような熱さ(輻射熱)が特徴です。
注意点として、ロウリュが許可されていないドライサウナのストーブに水をかけるのは絶対にやめましょう。
ロウリュを想定していない電気ストーブは故障や火災の原因となる可能性があり非常に危険です。
ドライサウナは、あくまで「乾燥」しているからこそ、あの高温が安全に保たれています。
このタイプのサウナでは、僕は「喉の乾燥を防ぐこと」を重視し、熱くても鼻呼吸を徹底します。
カラカラの高温サウナで一気に体を温め、キンキンに冷えた水風呂に一気に肩まで浸かる!
この「強烈な温度差」こそが、ドライサウナの醍醐味です。
慣れないうちは鼻で呼吸をするのもつらいかもしれませんが、慣れてしまえば深い呼吸を意識して、より集中できるので徐々に慣れていきましょう。
③ スチームサウナ(& 塩・ハーブサウナ)
- 特徴: 低温・高湿(40℃~60℃)。ボイラーによる蒸気。
- 楽しみ方: 美肌、リラックス、香りを楽しむ
基本分類の「湿式サウナ」の代表格が、このスチームサウナです。
ボイラーで発生させた蒸気(スチーム)を室内に充満させるため、湿度は常に100%近く。視界が真っ白になることもあります。
温度自体は低いため、息苦しさはほとんどありません。むしろ、深い呼吸で湿った空気を取り込むのが気持ちいいサウナです。
ハーブの香りが加えられていることも多く、その香りに集中することで、より深いリラックス効果が得られます。

美肌効果を最大化する!塩サウナの正しい入り方
スチームサウナとセットになっていることが多い「塩サウナ」。美肌効果が高いと人気ですが、正しい入り方を知らないと肌を傷つける原因にも。
僕が実践している効果的な入浴法をステップでご紹介します。
- 体を温め、汗を出す まずは塩を体に塗らずに、5分ほどスチームで体を温めます。肌が汗ばんできて、毛穴が開いてきたのを感じるのがポイントです。
- 塩を「乗せる」ように塗る 汗をかいたら、塩を手に取り、肌に優しく乗せるように塗っていきます。ここで絶対にやってはいけないのが、ゴシゴシと擦り込むこと。塩で肌が傷ついてしまいます。
- 汗で自然に溶かす 塩を乗せたら、再びサウナ室でじっくりと温まります。すると、自分の汗で塩がゆっくりと溶け出し、ペースト状になっていきます。この「汗で塩を溶かす」プロセスが最も重要です。
- 優しくマッサージ(お好みで) 塩が完全に溶けて液体状になったら、その液体で肌を優しく撫でるようにマッサージするのも良いでしょう。塩の浸透圧でさらに発汗が促され、毛穴の汚れを排出する効果が期待できます。
- 丁寧に洗い流す サウナから出たら、シャワーでしっかりと塩を洗い流します。この時も、タオルでゴシゴシ擦らないように注意しましょう。
この手順で入ると、肌はツルツル、スベスベに。僕も、肌のコンディションを整えたい時には必ず塩サウナを利用しています。
ちなみに、塩サウナの後は…?
「塩サウナの後は、水風呂に入るの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。結論から言うと、もちろんOKです!
塩サウナも立派なサウナなので、基本の「サウナ→水風呂→外気浴」のサイクルで楽しむのが王道です。
じっくり温まった後に水風呂でクールダウンすれば、高温サウナとはまた違った、マイルドで心地よい「ととのい」を体験できます。
ただし、ドライサウナほど体温が上がらないため、水風呂が冷たく感じすぎることもあります。
その場合は無理せず、ぬるめのシャワーやかけ水で汗を流し、そのまま外気浴に移るだけでも十分に気持ちいいですよ。
自分の体調や好みに合わせて、最適なクールダウンの方法を見つけてみてください。
3. 構造と熱源で選ぶ特殊サウナ
サウナの世界は奥深く、基本タイプ以外にもユニークな構造や熱源を持つものが存在します。
これらを知っておくと、サウナ施設選びがさらに楽しくなりますよ。
① 個性派ストーブの世界(タワー型 / isnessなど)
サウナ室の「心臓」とも言えるストーブ。近年は個性的な高性能ストーブが増えており、ストーブの種類で施設を選ぶファンも少なくありません。
タワーストーブ (iki / Harvia / SAWO / EOS)
サウナ室の中央にそびえ立つ、石のタワー。
この分野の代表格が、フィンランドの「IKI-Kiuas社」の『ikiストーブ』や、世界最大手「Harvia社」の『Legend』
同じくフィンランドの「SAWO社」の『Tower』シリーズです。
桁違いに多くのストーンを蓄熱するため、ロウリュをしても温度が下がりにくく、パワフルで安定した蒸気を楽しめます。
また、ドイツの高級メーカー「EOS社」のストーブも、その洗練されたデザインと性能で知られています。
メーカーによって熱の質や蒸気の広がり方が微妙に異なるため、その違いを体感するのもサウナの醍醐味です。
isness (イズネス)
METOS(メトス)社の『isness』は、「ガス遠赤外線」と「サウナストーン(ロウリュ)」を組み合わせた日本独自の高性能ハイブリッドストーブです。
遠赤外線で体の芯を温めつつ、同時にロウリュで湿度と熱波も生み出せるという、まさに”いいとこ取り”のストーブ。
従来のガスストーブでは不可能だったロウリュを実現し、サウナーから絶大な支持を集めています。

ロッキーサウナ
サウナストーンを多く配置した対流式のストーブです。安定した熱と湿度を生み出し、比較的穏やかでじっくりと入れる熱環境が特徴です。
② 遠赤外線サウナ(マグマ式など)
- 特徴: 遠赤外線ヒーターが壁に埋め込まれており、空気を介さず体を直接温める。
- 体感: 室温は低め(60℃前後)で息苦しくないのに、体の芯からじっくり温まる。
「温度計は60℃なのに、5分もすると玉のような汗が吹き出してくる」 そんな不思議な体験ができる遠赤外線サウナです。
フィンランド式やドライサウナが「対流熱(熱い空気)」で体を温めるのに対し、遠赤外線は体を直接「輻射熱」で温めます。
日向ぼっこでポカポカするのと同じ原理ですね。
室温が低いので、高温サウナが苦手な人でもリラックスして長めに入ることができます。
僕はこのタイプのサウナを、「体のコンディションを整えたい時」や「質の良い汗をじっくりかきたい時」に利用します。
息苦しさがないので、思考を巡らせたりするのにも向いていますね。
ただし、その特殊な構造から設置されている施設はまだ少なく、見つけたらラッキーなサウナの一つです。
例えば、日本初のパブリック型マグマスパ式サウナとして知られる「スゴイサウナ」や、大阪の「HAAAVE.(ハーヴェ)」などで体験することができます。
もし旅先などで見つけた際は、ぜひそのユニークな温まり方を体験してみてください。
③ バレルサウナ

- 特徴: 「バレル=樽」の名前の通り、木製の樽を横にしたような独特の形状。
- 体感: 丸い形状により熱が均一に循環し、マイルドで優しい熱に包まれる。
もともとはアウトドアや個人のサウナで人気が急上昇しましたが
近年ではその魅力から、温浴施設の外気浴スペースなどに導入されるケースが非常に増えています。
最大の特徴は、なんと言ってもその可愛らしい樽型のフォルム。
しかし、この形はデザイン性だけでなく、機能的にも非常に優れています。
角がない円形の構造は、ストーブで温められた空気が壁に沿ってスムーズに循環(対流)するのを助けます。
これにより、サウナ室内の温度ムラが少なくなり、どこに座っても均一でマイルドな熱を感じることができるのです。
僕も頻繁に、温浴施設に設置されたバレルサウナに入ることがありますが、外気浴スペースに直結する「離れ」のような感覚で
木の香りと優しい熱に包まれる静かな時間は、照明も控えめに設定されていることが多く、瞑想に最適です。
サウナ室から出てすぐに外気に触れられて、新鮮な空気を味わえる、最高の動線も魅力的です。
④ テントサウナ
- 特徴: 持ち運び可能で、好きな場所に設置できるアウトドア専用サウナ。
- 体感: 自然との一体感。薪ストーブならではの柔らかい熱。
ここ数年で一気に人気が爆発したのが、このテントサウナです。 その最大の魅力は、なんと言っても「ロケーションの自由度の高さ」。
川のほとり、湖畔、森の中など、好きな場所に自分たちの手でサウナ空間を作り上げることができます。
熱源には薪ストーブを使うことが多く、揺らめく炎を眺めながら入るサウナは格別です。薪ストーブが生み出す熱は電気式に比べて柔らかく、じっくりと体を温めてくれます。
僕も川のほとりでテントサウナを体験しましたが、サウナで温まった体に川の水が天然の水風呂となり
木々のざわめきを聞きながら外気浴をする時間は、まさに至福の一言。
運搬や、設営など手間はかかりますが、施設で体験するサウナとは全く違う
「究極のアウトドアアクティビティ」としての魅力があります。

4. 【上級者編】最高のサウナ室の把握術
さて、ここまではサウナの「種類」という、いわば施設のカタログスペックを見てきました。
しかし、同じ種類のサウナでも、なぜか「今日のサウナは最高だった」「今日はイマイチだった」と感じる日がありますよね。
その違いを生み出しているのが、サウナ室内の「コンディション」です。
ガチ勢と呼ばれるサウナ好きは、温度計の数字に頼るのではなく、自らの五感を使い、その日のサウナ室のコンディションを瞬時に把握しています。
ここでは、僕が意識している「把握術」を3つのステップでお伝えします。これができれば、あなたも間違いなく上級者の仲間入りです。
① 体感温度を決める「3つのカギ」を肌で感じる
まず、サウナ室に入ったら、温度計の数字よりも先に、肌で「温度・湿度・風」の3つの要素を感じ取ることに集中します。
| 要素 | 意味合い | 上級者のチェックポイント |
|---|---|---|
| 温度(℃) | 熱エネルギーの総量、単純な暑さ | 温度計の高さと位置を基準に、座る場所の熱さを推測する。 |
| 湿度(%) | 熱の伝わりやすさ、感じ方(熱の質) | 肌にまとわりつく熱の感覚を確かめる。ロウリュによる変化を感じ取る。 |
| 風(m/s) 空気の流れ | 熱交換の促進体感温度の上昇 | ロウリュやアウフグースで熱が運ばれてくる感覚、肌の上の熱のバリアが剥がされる感覚を捉える。 |
この3つのバランスが、その日の「体感温度」を作り出しています。
② 熱の流れを「読む」技術
次に、サウナ室内の「熱の流れ」を読み解きます。熱は一か所に滞留しているわけではなく、常に動いています。

上下の温度差(段差の活用)
これは基本ですね。熱い空気はまず上に溜まるため、上段ほど熱く、下段はマイルドになります。
僕はその日の体調によって、「今日はガツンと上段で」「今日はじっくり下段で」と使い分けています。
水平方向の熱の流れ(ストーブと排気口)
ここからがマニアックな視点です。サウナ室の空気は
「ストーブで熱せられ上昇 → 天井を伝って広がる → 冷やされて下降 → 床近くの排気口から抜ける」
という大きな対流を起こしています。
つまり、必ずしも「ストーブの真横が一番熱い」とは限らないのです。
僕も昔はストーブの前に座りがちでした。
ある時、最上段の排気口から一番遠い隅の座席が、熱が溜まりやすく、ストーブ前より熱く感じられることに気づきました。
その施設の空気の流れを読み、「自分だけのホットスポット」を見つけ出すのも、サウナの大きな楽しみの一つです。
③ 空間の質を決める「材質」と「香り」
最後に、空間全体の質を決定づけるのが、壁や床に使われている「材質」、そして空間に満ちる「香り」です。
木材は、香りによるリラックス効果だけでなく、熱伝導率の違い(熱くなりにくさ)によって、サウナ室の快適性を大きく左右します。
ここでは代表的な木材とその特徴を見ていきましょう。
ヒノキ(檜)
日本を代表する高級木材。清々しくリラックス効果の高い香りが特徴で、抗菌作用もあります。
美しい木目と肌触りの良さから、多くのサウナで壁やベンチに使われている、日常でも親しみのある木材です。
スプルース(米唐檜)
フィンランドのサウナで最も一般的に使われる木材の一つ。白く美しい木肌で、節があるのが特徴。
香りは控えめですが、コストと品質のバランスに優れています。
レッドシダー(米杉)
甘く、少しスパイシーな独特の香りが人気。耐久性と耐水性が高く、赤みがかった美しい色合いが特徴です。
僕もこの香りのサウナに入ると、森林浴をしているような深いリラックス感を得られます。
アスペン
節がほとんどなく、白く滑らかな木肌が特徴。熱伝導率が非常に低いため、ベンチ材として最適です。
長時間座っていてもお尻が熱くなりにくいという大きなメリットがあります。香りはほとんどありません。
ケロ
サウナ好きの憧れである「木の宝石」。
フィンランドのラップランドで立ち枯れた樹齢数百年のパイン材です。
ケロサウナに入ると、他にない芳醇な香りと、壁からじんわりと伝わる、驚くほど柔らかい輻射熱に包まれ、別次元の心地よさを体験できます。
これらの木材が持つ静かな香りに加え「アロマロウリュ」も空間を彩る重要な要素です。
ロウリュ水に使われるアロマオイルや、ヴィヒタ(白樺の若枝を束ねたもの)が放つ
生命力あふれる香りは、サウナ体験をさらに豊かで特別なものにしてくれます。
壁に背中を預けた時に感じる熱の柔らかさ、部屋全体に満ちる木々とアロマの香り。これらが一体となって、最高のサウナ体験は完成するのです。

5. まとめ:自分だけの「最高のサウナ」を見つける旅へ
今回は、サウナの基本的な種類から、上級者が実践するサウナ室の把握術までを徹底的に解説してきました。
この記事を読む前のあなたと、今のあなたとでは、サウナ施設を選ぶ基準が少し変わったのではないでしょうか。
もはや、温度計の数字や「ドライ」か「フィンランド式」か、という単純な分類だけでは満足できないはずです。
基本となる「乾式」「湿式」の違いを理解して、ロウリュがもたらす湿度の重要性を知り
iki、Harvia、isnessといった個性豊かなストーブの存在に心躍らせ、遠赤外線やバレルサウナといった特殊な構造の魅力を学ぶ。
そして何より、これからはどんなサウナ室に入っても、
「今の熱の質(湿度)はどうか?」 「空気の流れはどこで淀んでいるだろうか?」 「この木の香りは何だろう?」
と、自らの五感をフル活用して、その空間を把握できるようになったはずです。
サウナは、知れば知るほど奥が深い世界です。
ぜひ、この記事で得た知識を片手に、色々なサウナを体験してみてください。
そして、温度計の数字に一喜一憂することなく、あなた自身の感覚を信じて、自分だけの「最高のセッティング」を見つけ出す旅を楽しんでください。
あなたのサウナライフが、より豊かで実りあるものになることを願っています。